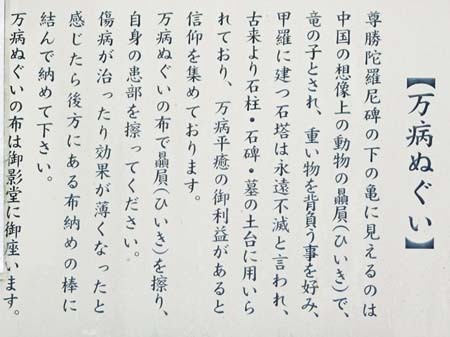昨日(2/21)の朝は、冷え込みました。もちろん氷点下の気温です。雪が降る降ると天気予報が騒いています。でも、私のところでは、雪雲が流れ込んでこずに雪は降りませんでした。大雪のところには申し訳ないような状況です。でも、お天気は曇り空で、本当に寒々とした景色の一日でした。
朝の仕事場の方は普段はバイク通勤なのですが、雪、積雪の予報だったことから、家族から「絶対にバイクで行かないで、転んで怪我をしても一切面倒を見ませんので」と言われたとことで、バスで来られたそうです。確かに雪のある路面は二輪は特に転倒の危険が大きいですよね。朝の職場の平均年齢は高いので、転んで骨折でもしたら、下手をすると歩けなくなる可能性もありますよね。何せ、通勤時間帯が早朝で、まだ雪が解けいないことも多いので。
その方が、昨日に、歩いている姿を見ましたが、植物園まで地下鉄もあるのに歩いて行かれているのですか?と ハイ、地下鉄の電車を待っている時間を考えるとあまり変わらないのでと私。それで、元気で、歩くのが早いのですねと(^^)/ 私は、スポーツクラブに通うよりもいいですよ。タダですし、自然にも触れられしねと。
さてさて、そんな植物園で見かけたタイトルの話題です。
◇トキリマメ(吐切豆)マメ科
トキリマメは、本州、九州、朝鮮半島の山野にはえるマメ科のつる性多年草。葉は先のとがった卵形の小葉3枚からなり、下面に黄色の腺点があります。7~9月、葉腋から短い花穂を出し、黄色で長さ約1cmの蝶形花を十数個密につけます。
豆果は繭形の楕円形で、中に2個の黒色の種子があり、熟すと裂開します。さやが赤いのでベニカワとも言います。
そんなトキリマメの種は年を越しても鞘から中々落ちずぶら下がっています。いつもでもあるのを不思議に思い調べてみました。
それによると、それはトキリマメの繁殖戦略の一部とのことです。トキリマメの種子は堅い殻で保護されており、成熟するまで莢(さや)の中にしっかりと固定されています。以下の理由が考えられるそうです。
〇成熟と繁殖:種子が十分に成熟しないうちに落ちることは、発芽の成功率を
下げることになります。種子が莢の中で完全に成熟するまで
保護されることで、発芽の可能性が高まります。
〇分 散:トキリマメの種子は風や動物によって分散されることがあります。
種子が成熟してから莢が開いて種子が放出されることで、
より広範囲に分散される可能性があります。
〇保 護:種子が早く落ちると、地面で捕食されるリスクが高まります。
莢の中で保護されていることで、捕食者から守られることがあります。
これらの理由から、トキリマメの種子は成熟するまで莢の中にしっかりと固定され、中々落ちない特性を持っているとのことです。
その戦略もすごいですね。どこでそんな知識を学んだのでしょうね。
SSブログ閉鎖に伴い、移行しました。
新しいブログの移行先は、Seesaaブログで「早起きおっさんの撮影日誌」←ここをクリックすると見られます。新しいブログ先も登録をお願いいたします。
★おまけのネタ
このブログでも1回登場していますが、またまた気になり撮影したので登場です。
せっかく撮影したのでお披露目です。
カラスザンショウ(烏山椒)ミカン科
葉痕が顔のように見えます。見えますよね!
葉が落ちた後の皿状に大きくえぐれている部分が葉痕です。
葉痕は丸みのある三角形。維管束痕が3つで目と口に見え、上にある冬芽はおでこか角か、いろいろ想像ができます。ネタは使いまわしですが、画像は新しく撮影したものですやじる←言い訳(-_-メ)
**************************************************
すーさんの「撮植(さつしょく)日記」
↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。
ご意見をいただければ最高です。
**********************************************
【今日は何の日】
22日(土) 先勝 [旧暦一月二十五日]
【猫の日】
2月22日を猫の鳴き声
「ニャン・ニャン・ニャン」の語呂合わせから。
猫の日制定委員会が1987年(昭和62年)に制定した。
その趣旨は、「猫と一緒に暮らせる幸せに感謝し、猫とともにこの喜びをかみしめる日」である。
【世界友情の日(創始者の日)】
ボーイスカウト運動の創始者であるベーデン・パウエル卿夫妻の誕生日が同じというこの日を記念して制定された。
彼はイギリスの陸軍出身。
【食器洗い乾燥機の日】
食器洗い乾燥機によって食後のゆとりができることから。
夫婦にっこり「2(ふう)2(ふ)2(にっこり)」の語呂合わせ。
日本電機工業会により制定された。
朝の仕事場の方は普段はバイク通勤なのですが、雪、積雪の予報だったことから、家族から「絶対にバイクで行かないで、転んで怪我をしても一切面倒を見ませんので」と言われたとことで、バスで来られたそうです。確かに雪のある路面は二輪は特に転倒の危険が大きいですよね。朝の職場の平均年齢は高いので、転んで骨折でもしたら、下手をすると歩けなくなる可能性もありますよね。何せ、通勤時間帯が早朝で、まだ雪が解けいないことも多いので。
その方が、昨日に、歩いている姿を見ましたが、植物園まで地下鉄もあるのに歩いて行かれているのですか?と ハイ、地下鉄の電車を待っている時間を考えるとあまり変わらないのでと私。それで、元気で、歩くのが早いのですねと(^^)/ 私は、スポーツクラブに通うよりもいいですよ。タダですし、自然にも触れられしねと。
さてさて、そんな植物園で見かけたタイトルの話題です。
◇トキリマメ(吐切豆)マメ科
トキリマメは、本州、九州、朝鮮半島の山野にはえるマメ科のつる性多年草。葉は先のとがった卵形の小葉3枚からなり、下面に黄色の腺点があります。7~9月、葉腋から短い花穂を出し、黄色で長さ約1cmの蝶形花を十数個密につけます。
豆果は繭形の楕円形で、中に2個の黒色の種子があり、熟すと裂開します。さやが赤いのでベニカワとも言います。
そんなトキリマメの種は年を越しても鞘から中々落ちずぶら下がっています。いつもでもあるのを不思議に思い調べてみました。
それによると、それはトキリマメの繁殖戦略の一部とのことです。トキリマメの種子は堅い殻で保護されており、成熟するまで莢(さや)の中にしっかりと固定されています。以下の理由が考えられるそうです。
〇成熟と繁殖:種子が十分に成熟しないうちに落ちることは、発芽の成功率を
下げることになります。種子が莢の中で完全に成熟するまで
保護されることで、発芽の可能性が高まります。
〇分 散:トキリマメの種子は風や動物によって分散されることがあります。
種子が成熟してから莢が開いて種子が放出されることで、
より広範囲に分散される可能性があります。
〇保 護:種子が早く落ちると、地面で捕食されるリスクが高まります。
莢の中で保護されていることで、捕食者から守られることがあります。
これらの理由から、トキリマメの種子は成熟するまで莢の中にしっかりと固定され、中々落ちない特性を持っているとのことです。
その戦略もすごいですね。どこでそんな知識を学んだのでしょうね。
SSブログ閉鎖に伴い、移行しました。
新しいブログの移行先は、Seesaaブログで「早起きおっさんの撮影日誌」←ここをクリックすると見られます。新しいブログ先も登録をお願いいたします。
★おまけのネタ
このブログでも1回登場していますが、またまた気になり撮影したので登場です。
せっかく撮影したのでお披露目です。
カラスザンショウ(烏山椒)ミカン科
葉痕が顔のように見えます。見えますよね!
葉が落ちた後の皿状に大きくえぐれている部分が葉痕です。
葉痕は丸みのある三角形。維管束痕が3つで目と口に見え、上にある冬芽はおでこか角か、いろいろ想像ができます。ネタは使いまわしですが、画像は新しく撮影したものですやじる←言い訳(-_-メ)
**************************************************
すーさんの「撮植(さつしょく)日記」
↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。
ご意見をいただければ最高です。
**********************************************
【今日は何の日】
22日(土) 先勝 [旧暦一月二十五日]
【猫の日】
2月22日を猫の鳴き声
「ニャン・ニャン・ニャン」の語呂合わせから。
猫の日制定委員会が1987年(昭和62年)に制定した。
その趣旨は、「猫と一緒に暮らせる幸せに感謝し、猫とともにこの喜びをかみしめる日」である。
【世界友情の日(創始者の日)】
ボーイスカウト運動の創始者であるベーデン・パウエル卿夫妻の誕生日が同じというこの日を記念して制定された。
彼はイギリスの陸軍出身。
【食器洗い乾燥機の日】
食器洗い乾燥機によって食後のゆとりができることから。
夫婦にっこり「2(ふう)2(ふ)2(にっこり)」の語呂合わせ。
日本電機工業会により制定された。
昨日(2/20)の朝は、冷え込みました。こちらでも氷点下のスタートでした。それでも、お天気は一昨日よりも安定した青空が広がり、風も弱かったことから一昨日よりも日中の気温は暖かく感じれました。
植物園の早咲きの花たちも太陽の光の中に春を感じられるのか、今年は遅めですが目を覚ましてきたようです。植物園では日陰の部分にはまだ雪も 残っていましたが、それでも光の中に春を感じれれるのでしょうね。植物たちは敏感です(^^)/
そんなまだ、寒さも残っている植物園で見かけたマンサク(満作) マンサク科の3種の登場です。
マンサクの花名の由来は、春に他に先立ち「まず咲く」から来ているとも言われています。雪の残る中でも花弁をヒラヒラとさせて春を呼び込んでいるような気もしますよね(^^)/
◇シナマンサク(支那満作)マンサク科
たびたび登場しているシナマンサクは、日本の「マンサク(満作)」よりも約一ヶ月ほど早くさきます。
ヒラヒラも大分伸びてきました。
◇ハマメリス・ほのか マンサク科
マンサクとシナマンサクとの交配種とのことです。その特徴が今一不明な私でした。
◇ニシキマンサク(錦万作)マンサク科
本州日本海側~北海道南西部に自生するマルバマンサクの花の色変わりといわれます。
花弁は4枚で基部に赤みを帯びるのがこのニシキマンサクの特徴です。
実は、このニシキマンサクには3日ほど前に咲いているのに気が付きました。マンサク類ではある見られますが、銘板がありませんでした。そこで、近くを歩いていた植物園ボランティアさんにお尋ねすると、分からないとい回答でした。そこで事務所に戻ったら職員さんに名札を下げて欲しいと伝えてくださいとお願いをしておきました。今回、私の願いが無事に届き銘板が下げられていました(^^)/
SSブログ閉鎖に伴い、移行しました。
新しいブログの移行先は、Seesaaブログで「早起きおっさんの撮影日誌」←ここをクリックすると見られます。新しいブログ先も登録をお願いいたします。
★おまけのネタ
福寿草の花が開いていたのを撮影できましたので登場です。
太陽の光を一杯浴びて温かく光り輝いて虫たちを呼んでいる姿です(^^)/


**************************************************
すーさんの「撮植(さつしょく)日記」
↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。
ご意見をいただければ最高です。
**********************************************
【今日は何の日】
21日(金) 赤口 [旧暦一月二十四日]
【食糧管理法公布記念日】
1942年(昭和17年)のこの日、国民食糧(主に米)の確保と国民経済安定を図るために食糧管理法が公布された。
1995年(平成7年)10月に同法が廃止された米の販売競争が進み、工夫が凝らされた銘柄が増えた。
【東京初の日刊新聞創刊の日】
1872年(明治5年)のこの日、東京で初めての日刊新聞「東京日日新聞」が創刊された。
後に毎日新聞に統合される。
植物園の早咲きの花たちも太陽の光の中に春を感じられるのか、今年は遅めですが目を覚ましてきたようです。植物園では日陰の部分にはまだ雪も 残っていましたが、それでも光の中に春を感じれれるのでしょうね。植物たちは敏感です(^^)/
そんなまだ、寒さも残っている植物園で見かけたマンサク(満作) マンサク科の3種の登場です。
マンサクの花名の由来は、春に他に先立ち「まず咲く」から来ているとも言われています。雪の残る中でも花弁をヒラヒラとさせて春を呼び込んでいるような気もしますよね(^^)/
◇シナマンサク(支那満作)マンサク科
たびたび登場しているシナマンサクは、日本の「マンサク(満作)」よりも約一ヶ月ほど早くさきます。
ヒラヒラも大分伸びてきました。
◇ハマメリス・ほのか マンサク科
マンサクとシナマンサクとの交配種とのことです。その特徴が今一不明な私でした。
◇ニシキマンサク(錦万作)マンサク科
本州日本海側~北海道南西部に自生するマルバマンサクの花の色変わりといわれます。
花弁は4枚で基部に赤みを帯びるのがこのニシキマンサクの特徴です。
実は、このニシキマンサクには3日ほど前に咲いているのに気が付きました。マンサク類ではある見られますが、銘板がありませんでした。そこで、近くを歩いていた植物園ボランティアさんにお尋ねすると、分からないとい回答でした。そこで事務所に戻ったら職員さんに名札を下げて欲しいと伝えてくださいとお願いをしておきました。今回、私の願いが無事に届き銘板が下げられていました(^^)/
SSブログ閉鎖に伴い、移行しました。
新しいブログの移行先は、Seesaaブログで「早起きおっさんの撮影日誌」←ここをクリックすると見られます。新しいブログ先も登録をお願いいたします。
★おまけのネタ
福寿草の花が開いていたのを撮影できましたので登場です。
太陽の光を一杯浴びて温かく光り輝いて虫たちを呼んでいる姿です(^^)/


**************************************************
すーさんの「撮植(さつしょく)日記」
↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。
ご意見をいただければ最高です。
**********************************************
【今日は何の日】
21日(金) 赤口 [旧暦一月二十四日]
【食糧管理法公布記念日】
1942年(昭和17年)のこの日、国民食糧(主に米)の確保と国民経済安定を図るために食糧管理法が公布された。
1995年(平成7年)10月に同法が廃止された米の販売競争が進み、工夫が凝らされた銘柄が増えた。
【東京初の日刊新聞創刊の日】
1872年(明治5年)のこの日、東京で初めての日刊新聞「東京日日新聞」が創刊された。
後に毎日新聞に統合される。
昨日(2/19)の朝は、冷え込みました。私の住む地域では空にはほぼ半月が見えて、放射冷却ということかキンキンに冷え込みました。夜明け前に家を出るときに月が見えるのに雪も舞います。これは、朝の仕事場のある京都市の北の方面ならもしかしたら雪景色かもとコンパクトカメラを懐に入れて近鉄、地下鉄を乗り継いて地上へ・・・残念、屋根の上には雪がありますが雪景色には程遠い景色でした。
朝の仕事が終わっていつものように植物園に向かう途中では、雪が、それもそれなりの雪の降り方です。これは積もるかと変な期待もしたのですが、すぐに青空が広がり雪が止みます。そんな雪と青空が交互に訪れるという不安定なお天気でした。
そんな雪の降るときに昨日に取り上げた「梅・香篆(こてん)」を見かけましたので、梅・香篆(こてん)と雪のツーショットということで!
SSブログ閉鎖に伴い、移行しました。
新しいブログの移行先は、Seesaaブログで「早起きおっさんの撮影日誌」←ここをクリックすると見られます。新しいブログ先も登録をお願いいたします。
★おまけのネタ
昨日は比叡山が雪雲で見え隠れを繰り返していました。
**************************************************
すーさんの「撮植(さつしょく)日記」
↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。
ご意見をいただければ最高です。
**********************************************
【今日は何の日】
20日(木) 大安 [旧暦一月二十三日]
【歌舞伎の日】
1607年のこの日、出雲阿国が江戸城で将軍徳川家康や諸国大名を前に、初めて「かぶき踊り」を披露したことに由来する。
彼女は京の四条河原で男装姿に刀を差して、異教の象徴である十字架を首から下げて踊っていたらしい。
【普通選挙の日】
1928年(昭和3年)のこの日、普通選挙法の成立を受け、日本ではじめての普通選挙が実施された。
【アレルギーの日】
1966年(昭和41年)のこの日、アレルギー性疾患の診断に大きく貢献したIgE抗体が石坂公成博士によって発見されたことを記念して、財団法人日本アレルギー協会が制定。
【多喜二忌】
『蟹工船』などを著した昭和期のプロレタリア文学作家、小林多喜二の命日。享年29。
特高警察の激しい拷問により築地警察署内で死亡。
朝の仕事が終わっていつものように植物園に向かう途中では、雪が、それもそれなりの雪の降り方です。これは積もるかと変な期待もしたのですが、すぐに青空が広がり雪が止みます。そんな雪と青空が交互に訪れるという不安定なお天気でした。
そんな雪の降るときに昨日に取り上げた「梅・香篆(こてん)」を見かけましたので、梅・香篆(こてん)と雪のツーショットということで!
SSブログ閉鎖に伴い、移行しました。
新しいブログの移行先は、Seesaaブログで「早起きおっさんの撮影日誌」←ここをクリックすると見られます。新しいブログ先も登録をお願いいたします。
★おまけのネタ
昨日は比叡山が雪雲で見え隠れを繰り返していました。
**************************************************
すーさんの「撮植(さつしょく)日記」
↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。
ご意見をいただければ最高です。
**********************************************
【今日は何の日】
20日(木) 大安 [旧暦一月二十三日]
【歌舞伎の日】
1607年のこの日、出雲阿国が江戸城で将軍徳川家康や諸国大名を前に、初めて「かぶき踊り」を披露したことに由来する。
彼女は京の四条河原で男装姿に刀を差して、異教の象徴である十字架を首から下げて踊っていたらしい。
【普通選挙の日】
1928年(昭和3年)のこの日、普通選挙法の成立を受け、日本ではじめての普通選挙が実施された。
【アレルギーの日】
1966年(昭和41年)のこの日、アレルギー性疾患の診断に大きく貢献したIgE抗体が石坂公成博士によって発見されたことを記念して、財団法人日本アレルギー協会が制定。
【多喜二忌】
『蟹工船』などを著した昭和期のプロレタリア文学作家、小林多喜二の命日。享年29。
特高警察の激しい拷問により築地警察署内で死亡。
昨日(2/18)の朝は、冷え込んだ京都でした。防寒具をまとい出勤でした。朝の仕事場まで行くと家々の屋根が白い、やはり前の晩は雪が降っていたのですね。空気が、風が冷たい訳ですね。
大学では、学生たちが春休みの間に、いろいろなメンテナンス作業が行われています。建物補修、古くなった設備の交換、樹木の剪定、そして私たちは教室や廊下のワックス掛けと、多くの人が新学期に迎える学生たちのために裏方と働いています。職員さんたちは、新入生を迎える準備に余念が無いと思います。しかし、まだ最後の入試が来週にありますが!
仕事で冷え切った体をヌクヌクの防寒服に着替えて、いざ植物園にと! 着替えのロッカーでは、皆さんからこんな寒くても行くの?と。ハイと答えて仕事の時よりも元気に出発でした(^^)/
そんな、植物園の梅園では、待ちに待った梅の花がやっと開花でした。本当に今年は咲き出すのが遅かったです。ズーっと大きく膨らんだ蕾のままで足踏み状態でした。やっと開花したのは、この梅園でも早咲きの品種で「梅・香篆(こてん)」バラ科です。他の梅の木はまだ蕾固しという状態でした。
「梅・香篆(こてん)」は、野梅系の八重白花咲品種で、いわゆる雲龍型で、大枝、小枝ともに横や斜めに曲がりつつ生長する品種です。実は好きな品種で、毎年気にしている梅の木なのです。今年も無事に開花が見られて良かったです。それは、私が元気に通っているという証ですね(^^)/
そんな梅・香篆(こてん)です。
花の上には露があり、その水滴の中に梅園が写ってました(^^)/
SSブログ閉鎖に伴い、移行しました。
新しいブログの移行先は、Seesaaブログで「早起きおっさんの撮影日誌」←ここをクリックすると見られます。新しいブログ先も登録をお願いいたします。
★おまけのネタ
福寿草(フクジュソウ)キンポウゲ科もでした。
この花は花弁を使って日光を花の中心に集め、その熱で虫を誘引しているそうです。その為、太陽光に応じて開閉(日光が当たると開き、日が陰ると閉じる)します。
もう少し、お日様が当たると花が全開するのですが・・・
**************************************************
すーさんの「撮植(さつしょく)日記」
↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。
ご意見をいただければ最高です。
**********************************************
【今日は何の日】
19日(水) 仏滅 [旧暦一月二十二日]
【強制収容を忘れない日】
1942年(昭和17年)のこの日、ルーズベルト大統領の命令によって日系アメリカ人が強制収容所へ転住させられた。
【プロレスの日】
1954年(昭和29年)に日本ではじめてプロレスの本格的な国際試合、力道山・木村政彦組対シャープ兄弟の試合が開催された。
大学では、学生たちが春休みの間に、いろいろなメンテナンス作業が行われています。建物補修、古くなった設備の交換、樹木の剪定、そして私たちは教室や廊下のワックス掛けと、多くの人が新学期に迎える学生たちのために裏方と働いています。職員さんたちは、新入生を迎える準備に余念が無いと思います。しかし、まだ最後の入試が来週にありますが!
仕事で冷え切った体をヌクヌクの防寒服に着替えて、いざ植物園にと! 着替えのロッカーでは、皆さんからこんな寒くても行くの?と。ハイと答えて仕事の時よりも元気に出発でした(^^)/
そんな、植物園の梅園では、待ちに待った梅の花がやっと開花でした。本当に今年は咲き出すのが遅かったです。ズーっと大きく膨らんだ蕾のままで足踏み状態でした。やっと開花したのは、この梅園でも早咲きの品種で「梅・香篆(こてん)」バラ科です。他の梅の木はまだ蕾固しという状態でした。
「梅・香篆(こてん)」は、野梅系の八重白花咲品種で、いわゆる雲龍型で、大枝、小枝ともに横や斜めに曲がりつつ生長する品種です。実は好きな品種で、毎年気にしている梅の木なのです。今年も無事に開花が見られて良かったです。それは、私が元気に通っているという証ですね(^^)/
そんな梅・香篆(こてん)です。
花の上には露があり、その水滴の中に梅園が写ってました(^^)/
SSブログ閉鎖に伴い、移行しました。
新しいブログの移行先は、Seesaaブログで「早起きおっさんの撮影日誌」←ここをクリックすると見られます。新しいブログ先も登録をお願いいたします。
★おまけのネタ
福寿草(フクジュソウ)キンポウゲ科もでした。
この花は花弁を使って日光を花の中心に集め、その熱で虫を誘引しているそうです。その為、太陽光に応じて開閉(日光が当たると開き、日が陰ると閉じる)します。
もう少し、お日様が当たると花が全開するのですが・・・
**************************************************
すーさんの「撮植(さつしょく)日記」
↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。
ご意見をいただければ最高です。
**********************************************
【今日は何の日】
19日(水) 仏滅 [旧暦一月二十二日]
【強制収容を忘れない日】
1942年(昭和17年)のこの日、ルーズベルト大統領の命令によって日系アメリカ人が強制収容所へ転住させられた。
【プロレスの日】
1954年(昭和29年)に日本ではじめてプロレスの本格的な国際試合、力道山・木村政彦組対シャープ兄弟の試合が開催された。
昨日(2/17)の朝は、この時期としたら暖かったのかな。その後も日中は陽射しの元では少しぬくもりも感じられましたが、午後からの風がどんどんと冷たく感じられました。これは今日は寒波の襲来と予報されているので心して完全なる冬支度で朝の仕事に出かける予定で準備をしております。
そんな今日は、24節気のひとつ「雨水」とのことです。雪が雨になり草木も芽を出し始め、日ごとに春らしくなるという意味があるとのことですが、これから寒波が・・・雨水で無く雪、それも日本海側では大雪との予報(-_-メ)
朝の仕事では、昨日から大学の校舎の廊下や教室などの床の水洗い、ワックス掛けがスタートでした。学生たちが休みの建物は暖房が入らず深々と冷えます。今日からの寒波はかなり堪えそうです。この寒さの中で、水を触るのはしもやけに(-_-メ)
さて、チョッと個人事業主の関係で得意先に寄り道したこともあり、途中下車して久しぶりに東寺さんをぶらりでした。東寺さんでは五重塔の特別拝観も行われていますが、もちろん私は有料エリアに入りません。
東寺さんも、そんなイベントも行われていますが、境内は本当に静かです、広さも感じられて伸び伸びとできました。
そんなぶらりとした東寺さんです。
〇五重塔
〇南大門と金堂
〇小子房
〇大日堂と境内など
その他にもいろいろと見どころが!
本当にこれだけの景色が無料で見られることが嬉しいです(^^)/
SSブログ閉鎖に伴い、移行しました。
新しいブログの移行先は、Seesaaブログで「早起きおっさんの撮影日誌」←ここをクリックすると見られます。新しいブログ先も登録をお願いいたします。
**************************************************
すーさんの「撮植(さつしょく)日記」
↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。
ご意見をいただければ最高です。
**********************************************
【今日は何の日】
18日(火) 先負 [旧暦一月二十一日]
【雨水】
24節気のひとつで立春から15日目にあたる。
雪が雨になり草木も芽を出し始め、日ごとに春らしくなるという意味がある。
【エアメールの日】
1911年(明治44年)にインドのアラハバードで開かれていた博覧会会場から、8キロ離れたナイニジャンクション駅まで6000通の手紙が初めて飛行機によって運ばれたことによる。
ところで、『星の王子さま』の作者サン=テグジュペリは郵便飛行機のパイロットであり、その体験は『夜間飛行』や『南方郵便機』などで描かれている。
【冥王星の日】
1930年(昭和5年)にアメリカ・ローウェル天文台のクライド・トンボーが、天王星の運行の乱れから予測されていた冥王星を発見した日。
15等星と暗い星で、そのイメージにちなみギリシア神話の冥府の神の名より「pluto(プルート)」と名付けられた。
その後、2006年8月24日、チェコのプラハで開催された国際天文学連合(IAU)の総会で、冥王星は惑星から外されて「矮(わい)惑星」となり、太陽系の惑星は「水金地火木土天海」の8個となった。
【かの子忌】
「芸術はバクハツだ」で有名な画家・岡本太郎の母で、歌人・小説家である岡本かの子の命日。
代表作は『老妓抄』『河明り』『生々流転』。
そんな今日は、24節気のひとつ「雨水」とのことです。雪が雨になり草木も芽を出し始め、日ごとに春らしくなるという意味があるとのことですが、これから寒波が・・・雨水で無く雪、それも日本海側では大雪との予報(-_-メ)
朝の仕事では、昨日から大学の校舎の廊下や教室などの床の水洗い、ワックス掛けがスタートでした。学生たちが休みの建物は暖房が入らず深々と冷えます。今日からの寒波はかなり堪えそうです。この寒さの中で、水を触るのはしもやけに(-_-メ)
さて、チョッと個人事業主の関係で得意先に寄り道したこともあり、途中下車して久しぶりに東寺さんをぶらりでした。東寺さんでは五重塔の特別拝観も行われていますが、もちろん私は有料エリアに入りません。
東寺さんも、そんなイベントも行われていますが、境内は本当に静かです、広さも感じられて伸び伸びとできました。
そんなぶらりとした東寺さんです。
〇五重塔
〇南大門と金堂
〇小子房
〇大日堂と境内など
その他にもいろいろと見どころが!
本当にこれだけの景色が無料で見られることが嬉しいです(^^)/
SSブログ閉鎖に伴い、移行しました。
新しいブログの移行先は、Seesaaブログで「早起きおっさんの撮影日誌」←ここをクリックすると見られます。新しいブログ先も登録をお願いいたします。
**************************************************
すーさんの「撮植(さつしょく)日記」
↑気ままに撮影した植物を掲載しています。よかったら見てやってください。
ご意見をいただければ最高です。
**********************************************
【今日は何の日】
18日(火) 先負 [旧暦一月二十一日]
【雨水】
24節気のひとつで立春から15日目にあたる。
雪が雨になり草木も芽を出し始め、日ごとに春らしくなるという意味がある。
【エアメールの日】
1911年(明治44年)にインドのアラハバードで開かれていた博覧会会場から、8キロ離れたナイニジャンクション駅まで6000通の手紙が初めて飛行機によって運ばれたことによる。
ところで、『星の王子さま』の作者サン=テグジュペリは郵便飛行機のパイロットであり、その体験は『夜間飛行』や『南方郵便機』などで描かれている。
【冥王星の日】
1930年(昭和5年)にアメリカ・ローウェル天文台のクライド・トンボーが、天王星の運行の乱れから予測されていた冥王星を発見した日。
15等星と暗い星で、そのイメージにちなみギリシア神話の冥府の神の名より「pluto(プルート)」と名付けられた。
その後、2006年8月24日、チェコのプラハで開催された国際天文学連合(IAU)の総会で、冥王星は惑星から外されて「矮(わい)惑星」となり、太陽系の惑星は「水金地火木土天海」の8個となった。
【かの子忌】
「芸術はバクハツだ」で有名な画家・岡本太郎の母で、歌人・小説家である岡本かの子の命日。
代表作は『老妓抄』『河明り』『生々流転』。